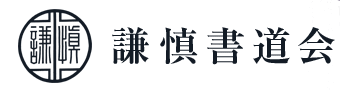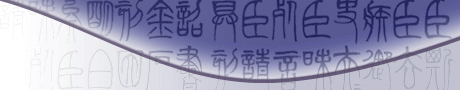呉昌碩の魅力はいったい何処にあるのだろうか。呉昌碩の生前中から幾度か展覧会が開かれ、また没後も、日本・中国はもとより香港、台湾でも数え切れないほど愛好者の支持を受けて開催されている。
日本では近年、逝世五十年に謙慎書道会主催による呉昌碩記念展が1977年に、また1994年には生誕150年記念展が各地で開催されたのは記憶に新しい。
出版においても、呉昌碩専揖は中国日本でも膨大な冊数にのぽり、呉昌碩芸術をあます所なく今日に伝え、現在我々がそれを豊富に目にすることができるのは幸福なことである。師・青山杉雨先生もライフワークの書道グラフ発刊3号(1956)にして表紙に呉昌碩の肖像を掲載、日本の書道界に一早く紹介しておられるが、その後幾度も呉昌碩を取り上げ、実に様々な角度からスポットをあて続けたことは周知の通りである。
呉昌碩は生涯を通してどれくらいの作品を残しているのであろうか。仮に、40歳から84歳に至るまで毎日一点作品を書いたとして約16,000点、画、篆刻の制作時間を考慮しても一万点は優に越すであろう。これに詩や尺牘類を合わせるとまさに超人としか言いようのない膨大な仕事を残しており、今世紀最後の文人と言わしめるにふさわしく、巨人といわれる所以であろう。
郁文社主催、逝世七十年呉昌碩展の大きな目的は、呉昌碩の年令における作品の推移を知るために企画したものである。そこで私の知る範囲の作品集を調査し、年令別に作品数を集計してみた。調査は1596点(干支のあるものに限った)に達し、一応統計として信用できるものとなったと思う。別表を見て(※下図)歴然としてわかることは、71歳から78歳まで極端に作品数が多くなる。これは多くの呉昌碩年譜に書画印を索めるものが多くなると記されているがそれを実証している。

年令別に細かく見てみると37歳の作品が多いが、これはこの年、生涯師としての禮をとった楊
 と出会い、また蘇州において呉雲を知り兩罍軒に寄寓している。また今回の展覧会に出陳作品中の、40歳の「無量壽佛」、45歳篆書巻子「畫紅梅」を與えた顧茶邨、そして金心蘭、呉秋農らと親交があった年でもあり、多くの刺激を得た一年であったための結果であろう。39歳、蘇州に転居するが、老母、妻子を迎え、生活のリズムが安定したためか、多作な歳となる。42歳も多く作品を残しているが今展覧会において容易に入手できず、途中でこの企画が頓挫しそうになった歳でもある。ちなみに48歳、50歳、58歳が同様であり、この3年は別表を見てもおわかりと思うが、激減している。50歳は上海の升吉里に転居、缶廬集を刊行しており、こちらの方が多忙であったのであろうか。51歳の年は日清戦争が勃発、これも減少の要因の一つといってよいだろう。
と出会い、また蘇州において呉雲を知り兩罍軒に寄寓している。また今回の展覧会に出陳作品中の、40歳の「無量壽佛」、45歳篆書巻子「畫紅梅」を與えた顧茶邨、そして金心蘭、呉秋農らと親交があった年でもあり、多くの刺激を得た一年であったための結果であろう。39歳、蘇州に転居するが、老母、妻子を迎え、生活のリズムが安定したためか、多作な歳となる。42歳も多く作品を残しているが今展覧会において容易に入手できず、途中でこの企画が頓挫しそうになった歳でもある。ちなみに48歳、50歳、58歳が同様であり、この3年は別表を見てもおわかりと思うが、激減している。50歳は上海の升吉里に転居、缶廬集を刊行しており、こちらの方が多忙であったのであろうか。51歳の年は日清戦争が勃発、これも減少の要因の一つといってよいだろう。
53歳リュウマチを病んだ年だが、別に作品数に変化はない。58歳から68歳まで平均減少傾向にある。61歳は西 印社の創立を計画しており、その影響もあるのではないだろうか。68歳は辛亥革命が起きており、やはり作品数は少ない。ところが71歳より急激に作品数が増えてくるのである。これ以後、彼の制作活動はピークを向かえることとなり、没年の84歳まで気満(金石の気)を感じさせる作品が多く、充実した線の姿勢にはまさに呉昌碩芸術の集大成と言える年月である。
印社の創立を計画しており、その影響もあるのではないだろうか。68歳は辛亥革命が起きており、やはり作品数は少ない。ところが71歳より急激に作品数が増えてくるのである。これ以後、彼の制作活動はピークを向かえることとなり、没年の84歳まで気満(金石の気)を感じさせる作品が多く、充実した線の姿勢にはまさに呉昌碩芸術の集大成と言える年月である。
この結論として時代の流れや、さらには呉昌碩自身の境遇によりそれが相重なることによって、生涯の書画制作数に素直に影響をうけた感がする。斯界最高という尊称をあたえられた呉昌碩の人間臭さ(魅力)のようなものをこの表により垣間見たような気がする。
53歳リュウマチを病んだ年だが、別に作品数に変化はない。58歳から68歳まで平均減少傾向にある。61歳は西
この結論として時代の流れや、さらには呉昌碩自身の境遇によりそれが相重なることによって、生涯の書画制作数に素直に影響をうけた感がする。斯界最高という尊称をあたえられた呉昌碩の人間臭さ(魅力)のようなものをこの表により垣間見たような気がする。
呉昌碩は自らの芸術を篆刻第一、書第二、画第三と言っているが、我々呉昌碩ファンからすると、すべての作か魅力的で、書画篆刻のどれをとっても第一と考えてしまう。
承知の通り、呉昌碩は生涯石鼓を習ったとされている。30歳頃には、泰の権量銘、琅瑯台刻石、泰山刻石、また鄧完白の篆隷を模索していたようであるが、39歳に書いた「詩経小戎四屏」はすでに石鼓文を多く参酌しており、石鼓の研鑚が進んでいる様子が伺える。没年まで一生のライフワークとして石鼓文を取り上げたが、それにただ型似を求めることだけにとどまらず、前出の権量銘、琅瑯台・泰山の筆意を混入し新意を表出させ自由に思うがままの運筆で古拙、迺逸を見事に表現してきた。
ただ私は、ライフワークの石鼓は本流として、呉昌碩の支流にある行草にすごく魅力を感じるのである。若年、楷書は鍾
徹底的に二家の書法をマスターした時点で石鼓文と出会い、篆書の筆法と融合し、筆勢は奔馳、蒼勁雄渾、興にのって一気呵成に書きあげた行草は明末清初の黄道周、倪元
呉昌碩の行草の魅力を掘り下げたが、特に尺牘、詩稿類、又は識語は卒意性を発揮し、たまらない表現法(行書、草書の配字また字群の疎密)は絶妙で行草体という独自の書体を確立させたといっても過言ではない。
呉昌碩は37歳の時、楊
参考図版として任伯年画「酸寒慰図」(※下図左)を載せたが、この画中、楊
 |
 |